職場で「ほめることが大事」とはよく言われます。
でも実際には、「ほめても甘やかすだけでは?」「叱らないと育たないのでは?」といった声も根強くあります。
私自身も、仕事の中で部下や後輩との関わり方に悩んだ経験がありました。
そんなときに出会ったのが、原邦雄さんの著書『ほめ育マネジメント』です。
この本は、単なる“ほめる”を超えて、組織や人材の成長を促す実践的なマネジメント手法を教えてくれます。
📘 ほめ育マネジメントとは?
「人はほめられるために生まれてきた」——この言葉を軸に、
社員の長所や成果を“発見”し、“言語化”し、“仕組み化”することで、
組織全体の信頼関係と業績を同時に高めていく考え方です。
導入企業は世界150社以上。離職率の低下や社員の自発性向上など、実績も豊富です。
🔍 実践の3ステップ
- STEP1:発見(長所・成果を見つける)
- STEP2:言語化(具体的に伝える)
- STEP3:仕組み化(継続的に文化として根づかせる)
この3ステップは、どんな職場でも応用可能です。
私自身も、ExcelやNotionを使って「ほめポイント」を記録する仕組みを試してみましたが、
チームの雰囲気が少しずつ変わっていくのを感じています。
🎯 叱ることも、信頼の一部
「ほめ育」は“ほめるだけ”ではありません。
叱る場面でも、相手の成長を願う姿勢があれば、信頼関係はむしろ深まります。
感情的ではなく、冷静に、具体的に伝えることが大切です。
「ほめる=甘やかす」ではない。業績が伸びない4つの誤解とは?
職場で「人を育てる」ことは、簡単なようでいてとても難しい。
特に、マネジメントに関わる立場になると、「どう接すればいいのか分からない」と悩む場面も増えてきます。
原邦雄さんの『ほめ育マネジメント』では、業績が伸びない組織に共通する「4つの誤解」が紹介されています。
この章は、ほめ育の本質を理解するうえでの“入口”とも言える内容です。
❌ 誤解①「叱らないと人は育たない」
多くの職場では、「厳しくしないと甘える」「叱ることで緊張感を持たせる」といった考え方が根強くあります。
しかし、叱ることが目的化してしまうと、信頼関係が崩れ、成長の機会を奪ってしまうことも。
▶︎ ほめ育では、「叱る前に、まずほめる」が基本。
信頼関係があるからこそ、叱る言葉も届くのです。
❌ 誤解②「ほめると甘える」
「ほめる=甘やかす」と誤解されがちですが、ほめ育では“根拠あるほめ方”を重視します。
「すごいね」ではなく、「〇〇の工夫が良かった」「△△の対応が助かった」といった具体的な言葉が鍵。
▶︎ ほめることで、自分の強みを自覚し、再現性のある行動につながります。
❌ 誤解③「できないことを指摘するのが教育」
欠点を指摘することが教育だと思っていませんか?
もちろん改善点を伝えることも必要ですが、「できていること」に目を向けることで、本人のモチベーションは大きく変わります。
▶︎ ほめ育では、「長所を伸ばす」ことが、結果的に短所の改善にもつながると考えます。
❌ 誤解④「業績は数字でしか評価できない」
数字は大切ですが、それだけでは人の成長や貢献度を測りきれません。
「プロセス」「姿勢」「周囲への影響」など、目に見えにくい部分にも価値があります。
▶︎ ほめ育では、数字以外の“見えない成果”にも光を当てることで、組織全体の活力を高めます。
🪴 誤解を解くことが、育成の第一歩
この4つの誤解を乗り越えることで、マネジメントの質は大きく変わります。
「ほめること」は、単なるテクニックではなく、信頼関係を築くための“土台”なのです。
私自身も、Excelで「部下の良かった行動メモ」を残すようにしてから、
フィードバックの質が変わり、相手の反応も前向きになったと感じています。
🔜 次回予告:長所を“お金”に換える経営とは?
次回は、第2章「長所をお金に換える経営」についてご紹介します。
「強みをどう業績に結びつけるか?」という視点は、個人にもチームにも役立つ考え方です。
あなたの職場では、どんな“誤解”が根づいていると感じますか?
ぜひコメントや感想で教えてください。次回もお楽しみに!
🔗 関連記事のご紹介
「ほめ育マネジメント」で信頼関係を築く方法を学んだあとに、リーダーとしての“覚悟”についても考えてみませんか?
吉田松陰の思想から学ぶリーダーの在り方は、現代のマネジメントにも通じるものがあります。
👉 覚悟とは才能ではなく、磨くもの|

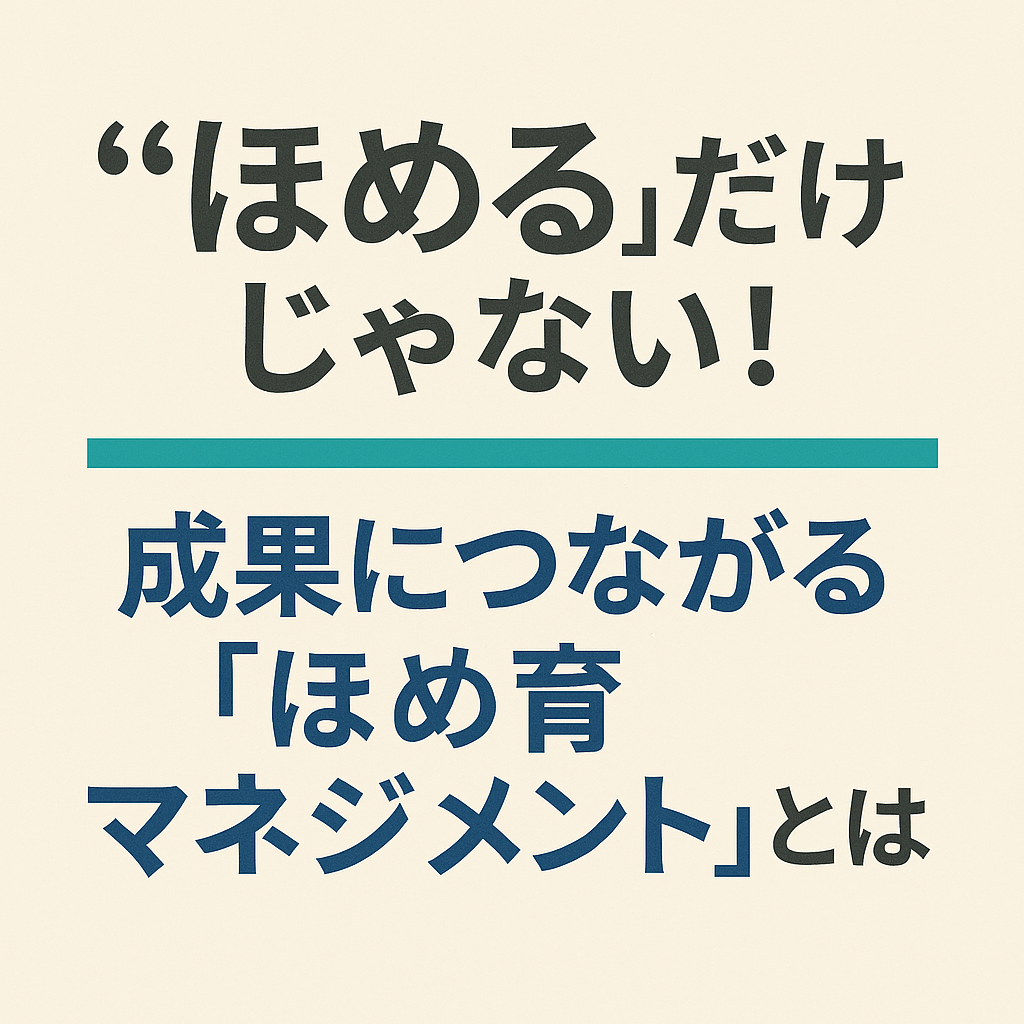

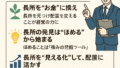
コメント